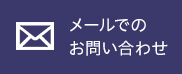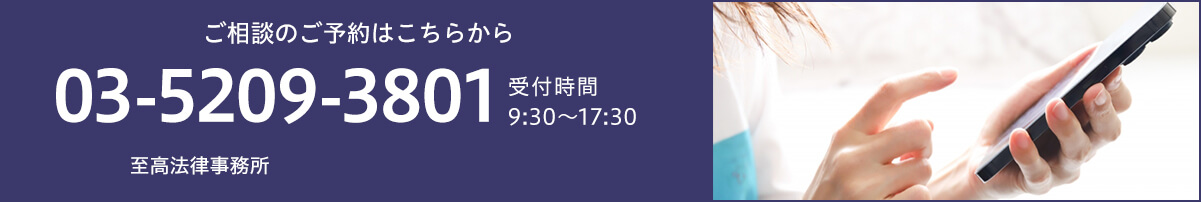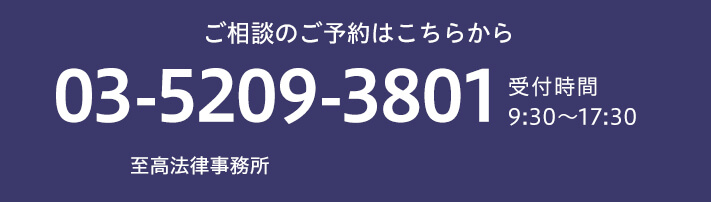1. 製造業における契約書の重要性
製造業は、原材料の調達から製品の設計、加工、販売に至るまで、多くの工程が連携して成り立っています。そのため、取引先との間で「どのような条件で」「どこまで責任を負うか」を明確にしておかなければ、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。そこで重要となるのが契約書です。
契約書とは、当事者同士が合意した内容を文書にしたものです。単なる口約束ではなく、証拠として残るため、万が一トラブルが起きたときに法的に保護されやすいのが特徴です。特に製造業では、以下のような場面で契約書が取り交わされることが多いです。
①委託者から製品またはその部品の発注を受ける場合
製造委託契約・取引基本契約書・個別契約書
②下請業者に製造を委託する場合
製造委託契約・取引基本契約書・個別契約書
③部品や原材料を仕入れる場合
売買契約・取引基本契約書・個別契約書
④製造委託を受ける前の検討段階など設計図や技術情報を共有する場合
秘密保持契約(NDA)
例えば、—ある企業が委託者から製品の製造の委託を受け、その一部の製造を再委託したところ、納期遅延や品質不良が頻発し、委託者へ損害賠償等を支払わざるをえなくなった。しかし、再委託先との契約書には「納期遅延時の違約金」や「検品基準」が明記されておらず、損害賠償を請求できなかった。―という事例は珍しくありません。このように、契約書は事前にリスクを想定し、トラブルを未然に防ぐための「盾」となるものです。
2. 製造業でよく使われる契約書の種類とポイント
製造業で登場する契約書には様々な種類があります。それぞれの契約書には押さえるべきポイントがあり、見落とすと不利な立場に立たされることがあります。
(1) 製造委託契約書
自社で設計した製品を他社に製造してもらう契約です。ここでは「仕様変更時の責任分担」「検品基準」「納期」「瑕疵担保責任(欠陥があった場合の修理・交換義務)」などを明確にすることが重要です。
(2) 売買契約書
部品や材料の売買に関する契約です。代金の支払条件、納品場所、引渡し時点でのリスク移転(所有権が誰にあるか)をしっかり決めておかないと、配送中の事故などで揉める可能性があります。
(3) 秘密保持契約(NDA)
製造業は技術力が競争力の源泉です。図面や試作品の情報が流出すれば大きな損失になります。NDAを締結しておけば、情報漏えい時に責任追及が可能です。
(4) 業務委託契約
製品の一部もしくは全部の製造、又は、製品の検査や物流などを外部に委託する場合に用いられます。成果物の範囲や再委託の可否、事故が起きた場合の責任分担を明記する必要があります。
これらの契約書はいずれも「雛形(ひながた)」が存在しますが、業種や取引内容によって必要な条項は大きく異なります。インターネット上の一般的な雛形をそのまま利用すると、自社のリスクに対応できないケースも多いため、注意が必要です。
3. 契約書で特に注意すべき条項
契約書には数多くの条項がありますが、製造業で特に重要なものを具体例とともに紹介します。
(1) 納期と遅延損害金
「納期を守ること」は製造業における信用の基盤です。納期遅延が発生した場合、どの程度の違約金を支払うのかを定めておくことが、トラブル防止につながります。
(2) 品質保証と検査
製品の不良率が高いと、リコールや取引停止につながります。契約書には検品方法、品質保証期間、不良品が発生した場合の処理方法を明記しておきましょう。
(3) 知的財産権の扱い
製品設計やノウハウが関わる取引では、「知的財産権(特許や商標などの権利)」が誰に帰属するかが大問題となります。例えば「共同開発した新製品の権利がどちらに帰属するのか」を曖昧にすると、将来の特許収益で揉める可能性があります。
(4) 損害賠償責任
契約違反や製品欠陥により発生した損害を、どこまで賠償するのかを決めておかないと、想定外の高額請求を受けるリスクがあります。
これらの条項は専門的で難しく感じられるかもしれませんが、契約書を作成・確認する際には必ず注目すべき項目です。
4. 契約トラブルの事例と教訓
実際に起こったトラブル事例を見てみましょう。
事例1:納期遅延による取引停止
ある企業は海外工場に製造を依頼しましたが、納期が数か月遅れました。契約書には遅延時の対応が記載されておらず、納期を守れないたびに顧客からのクレームが殺到。最終的には主要取引先を失いました。
教訓:契約書には必ず「納期遅延時の違約金」や「契約解除権」を盛り込むべきです。
事例2:品質不良によるリコール
部品供給契約を結んでいた会社から、不良率の高い部品が納品されました。契約書には品質保証の詳細がなく、リコール費用をすべて自社で負担する羽目に。
教訓:検査基準や不良品対応を明記することで、責任の所在を明確にしておく必要があります。
事例3:知的財産権の帰属を巡る紛争
共同で開発した製品の特許を巡って、取引先と裁判になった企業もあります。「特許は共同所有」と契約書に記載したものの、使用範囲や利益配分、それを決める手続きが定められておらず、事業化が進められませんでした。
教訓:知的財産権は「誰がどこまで利用できるか」または、そこまで具体的に決められない場合でも、それらを決める手続きを具体的に記載する必要があります。
このような事例からもわかるように、契約書を軽視すると企業活動そのものに大きな影響を及ぼします。
5. 契約書を弁護士に依頼するメリット
「自社でも雛形を作れるのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし、弁護士に依頼することで得られるメリットは大きいのです。
(1) リスクの見落としを防げる
弁護士は数多くの契約トラブル事例を知っています。そのため、企業が気づきにくいリスクを事前に洗い出すことができます。
(2) 自社の立場を最大限に守れる
契約は交渉です。相手に有利な条件が提示されたときも、弁護士が交渉に関与すれば、自社にとって不利にならないよう修正が可能です。
(3) 交渉力の強化
「弁護士にチェックしてもらっている」と伝えるだけで、相手は安易な要求をしづらくなります。結果的に有利な契約が結びやすくなります。
(4) 社内負担の軽減
契約書の確認には法的知識と時間が必要です。弁護士に任せることで、社内リソースを本業に集中させることができます。
6. まとめ ― 契約で企業を守る第一歩
製造業における契約書は、取引の安心と信頼を支える「盾」であり、トラブルを未然に防ぐ「予防策」です。納期、品質、知的財産、損害賠償など、見落とせば企業の存続に関わるリスクが潜んでいます。
雛形をそのまま使うのではなく、自社の取引内容に即した契約書を用意することが大切です。そのためには、経験豊富な弁護士のサポートが不可欠です。
私たち法律事務所では、製造業を中心とした多くの契約書作成・レビューに携わってきました。企業の実情に合わせたオーダーメイドの契約書を提供し、安心して事業を展開できるよう支援いたします。
契約に不安を感じている方、今まさに取引先との契約を控えている方は、ぜひ一度ご相談ください。初回相談では、具体的な事例を踏まえながら、自社に必要なポイントを整理するお手伝いをいたします。
企業の未来を守る第一歩として、契約書の見直しから始めてみませんか。
7.関連記事
製造業で顧問弁護士をお探しの方へ-クレーム対応・契約書トラブルは弁護士まで-
Last Updated on 2025年10月27日 by sicoh-law-com
 この記事の執筆者:至高法律事務所 |
| 事務所メッセージ 社会の課題に対し、私どもは「世のため、人のために尽くすことが、人間として最高の行為である」という理念にもとづき、これまで培ってきた法的技術やノウハウを駆使した創造的な解決策を提供することでこれを解決し、持続可能な人類・社会の進歩発展に貢献するという経営理念の実現に向けた挑戦を日々続けております。そして、「至高」という事務所名に込めた「社会正義の実現」、「社会の最大の幸福の実現」、「持続可能な人類社会の実現」に貢献するという高い志をもって努力をし続けて参ります。 |
お問い合わせはこちらから